生命保険の選び方|年代別、家族構成ごとに考えてみましょう
- 2019.05.12
- ファイナンシャルプランナー(FP) 生命保険

Contents
生命保険の選び方|年代別、家族構成ごとに考えてみましょう
生命保険の加入目的を知っておきましょう
生命保険の主な目的は4つあります。
- 遺族の保障
- 亡くなった後の整理金(お葬式代)
- 入院
- 貯蓄
大きく分けると、遺族の保障と亡くなった後の整理金は他人のための保険です。自分に万が一のことがあった時に誰かに渡す保険金なので自分のためではありませんよね。
そして入院を目的とした保険は、自分は存在してしていますよね。入院した時に自分が手術代を受取るのが入院時の保険なので自分のための保険と言います。
貯蓄は自分のための場合もありますし、家族や子どものため等用途は様々です。
以下ひとつずつ解説していきます。
①遺族の保障
自分に万が一のことがあった時に、残された遺族がお金に困らないようにするためです。
【事例】ご主人が収入の柱で、奥様が専業主婦でお子様が2人いるような世帯の場合はご主人がもし万が一のことがあった場合はそれ以降今までのお給料が奥様と子どもはなくなってしまいますので収入がなくなりますよね。
これをカバーするが遺族の保障を目的とした保険加入になります。
一般的には掛け捨ての保険でカバーします。「定期保険」「収入保障保険」というものが一般的です。どちらも呼び方は違えど、掛け捨ての保険です。
保険の見直しの定番は「収入保障保険」になります。保険料も構造的に割安になる仕組みになっています。
②亡くなった後の整理金(お葬式代)
よく独身の方が万が一の時のためのお葬式代くらいは・・というお話をよくされる方がいますが、自分に万が一のことがあったときに残された人が葬儀代で苦労しないようにということで加入をします。
地域によって平均的な葬儀代も異なりますので、一般的にはその地域の平均額くらいの保障を用意するのが良いでしょう。
ただし、高い地域でも250万弱なのでそれくらい貯金で何とかすることも可能なので優先順位としては亡くなった後の整理金としての保険加入は低いです。
亡くなった後の整理金は掛け捨ての保険は向かないので、終身保険で用意するのが一般的です。貯蓄タイプの保険になります。
したがって掛け捨てタイプよりもちょっと割高ですが、貯蓄性もある上万が一の時は解約して戻ってくるお金もあります。解約のタイミングによっては払ってきた金額よりも多くなる場合もあります。
このブログでは亡くなった後の整理金を用途とした生命保険の準備はあまり重要視していないので割愛いたします。
地域別の葬儀代でおおよその金額を調べて、例えば葬儀代相場200万の地域に住んでいる方は200万の終身保険に加入するだけです。
③入院
①遺族の保障と②亡くなった後の整理金の用途は
残された人が困らないように
するためのものでした。
この入院の保険というのは、生命保険の中の
「医療保険」というものでカバーすることになります。
入院した時に、手術をしたり、入院がした時の医療費を受取れるというものになります。最近では通院や1日入院したら5日分まとめて一時金で渡すなど様々なパターンがあります。
医療保険は自分に万が一のことがあった時の保険ではなく、病気の入院費や手術代を受取るものです。遺族の保障や亡くなった後の整理金と異なって
自分は生きていて、受取人も通常は本人が受取るという点が異なります。
④貯蓄としての機能
マイナス金利以降、実は保険の貯蓄としての機能は完全に衰退してしまっています。
日本の生命保険会社が持っている、通常の終身保険は貯蓄性があるのに20年預けても年代や付与している特約等があると払った金額より、解約をして受取れるお金の方が少なく損してしまう事例が以前よりも多くなってきています。
外貨建て保険というリスクはあるものの、利回りのよい商品は存在しています。銀行の普通預金や定期預金に預けるよりかははるかに利回りは大きいです。(但しリスクがあります。)
こちらのブログではこの④貯蓄としての機能についてはあまり重要視していないので割愛します。
②の亡くなった後の整理金と④の貯蓄としての機能はあまり重視する必要はないので、ここからは、遺族の保障と入院の保険についての考え方について年代別、家族構成別に見ていきましょう。
生命保険の選び方|遺族の保障編
遺族の保障を選ぶときに考えることは1つだけです
それは自分に万が一のことがあったら収入で困る人がいるか?いないか?です。
①自分に万が一のことがあったら困る人がいるパターン
自分が大黒柱で専業主婦の奥さんがいる、子どもがいるようなパターンです。
逆もしかりです。奥さんが看護師や公務員、ご主人が専業主夫やフリーターのようなケースも近年よくあるスタイルです。
あるいは住宅ローンを共有名義にしているケースもありますね。共働きで、夫婦でお互い月に手取り20万ずつ。うち住宅ローンは5万ずつ出し合っている。ような場合はどちらかの収入がなくなったら致命的です。(団信に加入をしていればよいかも知れませんが、片方の残債は残ります。)
②自分に万が一のことがあっても困る人がいないパターン
困らないというのはここでは金銭的にと思ってください。私なんかいなくなったって誰も悲しまないとかそういう意味ではありません。
ご主人が大黒柱で、奥様が専業主婦。そして奥さんが亡くなった場合。深い悲しみではありますが、金銭的には大黒柱が健在なので極端な話万が一の保障は必要ありません。
仮に葬儀代が心配であれば、前述の亡くなった後の整理金を目的とした生命保険を奥様がご加入しておく必要はあります。ただくりかえしになりますが、せいぜい多くても250万程度なので、あまり必要性はないかと思います。
ただ葬儀代だってばかにならない、いざというときにまとまった出費が不安ならば、必要金額分を前述の葬儀のサイト等で検索してその金額を終身保険で加入をするのが良いでしょう。
遺族の保障は遺族年金を考慮する
今仮に夫婦お互い30歳で日々の生活費が20万だったとします。65歳まで働き続けるとしたら単純計算で
現在から65歳までの年数・・・35年
月の生活費20万
1年・・・12カ月
必要保障額は35年×12カ月×20万=8400万
必要保障額は8400万!
意外と大きいですよね。ただ、実はこれ全部用意する必要が無いんです。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の仕組みは難しいので、リンクで遷移する人は興味のある人だけで大丈夫です。通常は保険会社の営業が計算してくれます。
個人事業主等は遺族基礎年金、
お勤めの方や公務員は遺族厚生年金を考慮すると
必要保障額はかなり削減され、それにともない毎月の保険料は少なくて済みます。万が一の時の保障を考えるときに、遺族年金を考えないと非常に損です。
そして以下超!注意点です↓↓
会社員のご主人ではなく、奥さんが亡くなった場合は遺族年金が出ない場合もありますので注意をして下さい。
但し、妻が亡くなった時の遺族年金はかなり夫の時よりも冷遇されています。
生命保険の選び方|遺族の保障編【まとめ】
遺族の保障は定期保険か収入保障保険という掛け捨ての保険で用意すること
遺族の保障は遺族年金を考慮すること。国民年金の人は遺族基礎年金のみ、お勤めの方は遺族厚生年金がある。
妻に万が一のことがあった場合の遺族年金は要件が厳しい

この記事を書いた人
ファイナンシャルプランナー金子 賢司
これまで1000件以上の家計、住宅ローン、生命保険、損害保険、資産運用の相談に携わる。UHBなどのテレビのコメンテーターや確定拠出年金等のセミナーを毎年約50回実施。CFP資格保有者。TLC(生命保険協会認定FP(TLC資格とは))、損害保険トータルプランナー、公式HP
- 前の記事
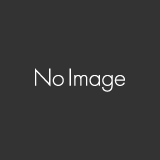
遺族厚生年金について 2019.05.12
- 次の記事

終身雇用が崩壊|安定したライフプランはオワコンの時代 2019.05.13